恩蔵絢子著『脳科学者の母が、認知症になる』(河出書房新社2018年10月発行)を手に取ったのは、父の認知機能がだいぶ低下してきて心配だという話をしたとき、私より10歳ほど年上の先輩編集者さんが「参考になるよ」と教えてくれたからだった。
著者のお母さんは、65歳でアルツハイマー型認知症と診断された。
「誰でも年をとれば認知症になる可能性がある」という認識はあったけれども、自分の母親にその疑いを持った時、この世の終わりかと思うくらいにショックだった。
と著者は冒頭で語っている。
だけど、ひとたび現実を受け入れたとき、一緒に暮らしている脳科学者だからこそ間近で行動や様子を徹底的に観察し、科学的知見から脳の仕組みを考察できるのではないかと思うに至る。そして二年半の記録が、この本に結実した。
読むと、アルツハイマー型認知症と脳について現在解明されている科学的知見を知ることができる。加えて、母親との日常生活で起きるトラブルによって著者が感じた苛立ちや、変化していく母のなかに「母らしさ」を探る過程で揺れる心情にも触れることができる。科学者としての視点のみで線引きせず、娘として人として抱くやるせなさにも目を向け、正直に語る姿勢に親しみを覚えた。
脳の仕組みについては、とにかく「なるほど!」と学ぶことが多かった。と同時に、変化していく親と向き合う著者の心情は、このブログに父のことをつづりながら私が父と過ごした今年夏以降のそれと重なることが多く、共感しきりだった。
現在の知見の大枠をざっくりまとめると、こんな感じだ。
アルツハイマー型認知症は、記憶を司る海馬の萎縮によって新しいことを覚えにくくなることから始まる。
原因は「脳の中にできた消化不良の粗大ゴミ」のような老人斑と神経原繊維変化で、それらが情報伝達を阻害することで症状が出る。
老人斑を取り除く薬の開発と臨床実験が進められていたが、老人斑のもとになるアミロイドβを取り除いても病の進行が止まらないという研究報告が2018年に出されている。
現状、85歳以上になると半数の人がアルツハイマー認知症を発症するが、決定的な治療薬はない。情報が脳内をうまく伝わらなくなっていき、次々に細胞が死んでいくことで脳の萎縮、認知障害、運動障害も現れるようになる。やがて歩く、飲み込むといった基本的な身体機能を司る脳部分にも損傷が起き、最終的には寝たきりになる。主要な死因原因は、嚥下障害などで栄養がとれなくなり、肺炎などの感染症になってしまうことだという。
では、治る術が見つかっていない認知症になると、私たちは絶望するしかないのだろうか。
著者は、アルツハイマー型認知症と脳のメカニズムに焦点を当てつつ、料理したり洗濯したりという日常の母の行動や家族との関係における反応を細やかに観察する。そして、母という役割や個人としての感情の表出としても分析する。さらに人の知性はIQ(Intelligence Quotient=知能指数)とか偏差値などの指標だけで決まるのではなく、EQ(Emotional Intelligence Quotient=感情的知能指数)も含めて捉えるべきだという研究なども参照しながら、認知症になっても豊かな感情が存在している母に「母らしさ」を肯定的に認めていく。そして著者が至る結論は、こうだ。
認知症は、その人らしさを失う病ではない。
しかも、哲学者カントの晩年がそうであったように、アルツハイマー型認知症になっても、人間が人間として尊重され感謝されるような環境にいれば、攻撃性は和らげることができる。自分の役割を持ち、安心できる居場所があれば、徘徊を防ぐこともできる。
そんな環境・状態を保つことは容易ではないかもしれないが、私たちはその可能性を探ることはできる。それを本書は示してくれる。
ここに摘み出したのは、書かれているエッセンスのほんの数滴でしかない。
超高齢化社会に突入している今、あなたの家族のために、そして自分のためにも、ぜひ読んでみてほしい。理解者が増えれば、認知症になっても幸せに生きられる社会がきっと実現できると思うから。
認知症になっても、「その人らしさ」は失わない。あたたかく親を見守るための知識と心構えを教えてくれた
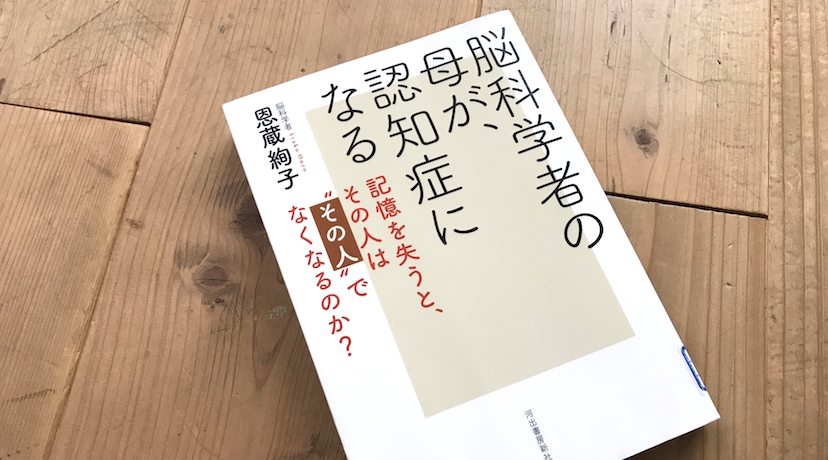 気になること
気になること
