2015年12月に原田病を発症し、当時住んでいた三鷹市内にあるK医大付属病院に入院した。その後も同病院でずっと定期的に検査・診察を受けていたのだが、2019年4月に転院を決意した。
転院を決意した理由には、2018年2月末に三鷹市から所沢市に引っ越して通院に片道1時間半ほどの時間と往復1280円の交通費がかかるようになったこともあったが、それと同じくらい、相性のよくない先生がほとほと嫌になってしまったという事情もあった。
K医大付属病院の眼科では、眼炎担当医師が複数名のチームで診察していて、どの医師に診てもらうかは、毎回、呼ばれて診察室に入らないとわからない仕組みになっている。
3年半以上通院していた私は、入院中から信頼していた30代くらいの女性のN先生のときは「あたり」、同世代と見られる中年女性のA先生のときは「はずれ」、そのほかの男性医師のときは「まあまあ」という心情をいつしか抱くようになっていた。そのA先生の「はずれ」のストレスが大きく膨らんだことが、転院を真剣に考えるきっかけになった。
なぜA先生が「はずれ」なのかというと、彼女の診察を受けると、なぜか私は気持ちが塞いでしまうからだ。診察室を出たあとにまで、A先生の言葉や眼差しがチクチクと心に刺さっているのを感じて滅入ってしまうのだ。
例えば、「白内障が進んでますね。まあ、年齢もありますから」というような、こうして文字にすれば、そんなありきたりのことに目くじら立てなくてもというほどのことだったりするのだが、前回の男性医師は「白内障が少し進んでますね。ステロイドの副作用だから仕方ないですが」と言っていたことを思い出すだに、A先生の後半部分の「年齢もありますから」はわざわざ付け加えなくてもいいんじゃない?と思ってしまう。というか、それよりも彼女のなんともいえない言葉の抑揚や目つきに、私は何らかのトゲを感じてしまうのだった(私のようにトゲを感じずに、彼女の言動を受け入れることができる人はいるんだろうか? 私が過敏だったのだろうか? それとも、誰にとっても「嫌な人」なんだろうか?……わからない)。
あるときA先生が、診察の最後に「目薬、何本出しますか?」と尋ねてきたことがあった。普段は何も問わずに医師が処方を出してくれるのが常だったから、にわかに本数を答えることが私にはできなかった。前回は何本だったか? いつもはどうだったか?……と記憶をたどろうとしている私を、彼女はあざけるように見ていた(ように私は感じた)。
「では、次回の診察までに必要な本数を」としどろもどろに告げると、「人によって違いますからねぇ。何度も外しちゃってたくさん使うおばあちゃんとかもいますから」と、私を斜めに見ながらA先生は言うのだった。「はぁ?」と不機嫌な思春期の子どものように疑問を呈しそうになるのをグッとこらえ、「では前回と同じ本数を」とぼそぼそと答えながら、「いったいなぜ彼女は本数を私に言わせる?」「自分の薬の必要量すら把握していない私はバカ?」「目薬を外しまくるおばあちゃんと私は同類?」……などという詮索が頭をぐるぐると巡り、腹立たしいような泣きたいような心細さになってしまったのだった。ああ、やだ。
転院を心に決めたのは、A先生が「あらぁ、所沢から来てるのねぇ」と嫌味な口調で尋ねてきた日だった。前回の診察は30代くらいの男性の医師で、たまたま混んでいて3時間もの待たされてうんざりしていたこともあって、思い切って「引っ越したので、転院を考えているのですがどうでしょうか?」と聞いてみたのだった。すると彼は、「安田さんの場合、発症からずっとここですし、通えない距離ではないなら転院しない方がよいと思います」と答えたのだった。その問答の申し送りが、きっとカルテのどこかに書かれていて、A先生の「あらぁ、所沢から来てるのねぇ」発言につながったのだと思われる。
彼女は言葉を継ぐ。「所沢ねぇ……病院はあるかしらね、どうかしら。まあ、転院したいなら紹介状は書きますよ、1枚ですけどね。そんなにたくさんは書けないですから」
……にわかに、所沢をバカにされたような気がしたり(実はまだ所沢にはそれほど地元愛を抱いていないから自分の反応が不思議でもあったが)、3年以上もの病歴を1枚ぽっきりの紹介状にすることが妥当なのか投げやりなのか判断できなかったり、彼女の口調をあまりに侮蔑的に感じてしまったりして、またまた腹立たしいような泣きたいような気持ちにさせられてしまったのだった。ああ、やだやだ。
「そんな言い方しなくてもいいんじゃないですか?」と食ってかかってもよかったと思う。「なんでそんな言い方をするんですか?」と苛立ちを表したってよかったと思う。
だけど、私はそういう妙な含意のある態度をとる人に対して、即、反射的に異議申し立てすることがなかなかできない。むしろ、何か私に問題があって相手の気を悪くさせてしまったのではないか?……と弱気になってしまう小心者だ。ましてや診察室という場で、相手が医師となるとさらに強く出ることができなくなってしまう。その自分の不甲斐なさが腹立たしくも情けなくもなり、さらに泣きたくなってしまう体たらくだ。トホホ。
「あらぁ、所沢から来てるのねぇ」と見下された(と私が感じてしまった)次の回、私は眼科の受付で「A先生ではない先生に診察をお願いします」と勇気を出して初めてリクエストを出した。
そしてその日、診察室で私を迎えたのは、眼炎担当チームのトップのS教授だった。その頃、私の原田病は左目に症状が再発して半年近く経っていて、点眼薬で症状は治まっていた。だから転院しても心配はないこと、そして、これまでの症状と治療の経緯を画像も添付してまとめて彼自身が紹介状を書くことを、S教授は落ち着いた口調で説明してくれた。ひと安心である。
しかし、これが普通の対応だよな、と今、これを書きながらあらためて思う。
転院することが、なぜあれほど胸をかきむしられるほど不安になってしまったかといえば、あのA先生の嫌味な対応ありきである。
かくして2019年4月を最後に、私は「A先生にあたったら嫌だな」というストレスなく病院に行けるようになった。往復約3時間と交通費1280円も不要になった。
近所の国立B医大付属病院には、徒歩でも行ける。待ち時間もたいてい1時間ほどで長くない。心穏やかに、3ヶ月に1回程度通っている。ここでは、診察してくれるのはいつも同じ30代くらいの男性医師だ。
「今回は何本にしましょうかねー?」と目薬の本数を聞かれるのは、すでにステロイド薬の治療が終わっていて、ドライアイ用の点眼薬だから使用頻度によって必要量が違うからだ。むろん質問の裏になにがあるか詮索するような局面はなく、そもそも彼の口調はいたって柔和でニュートラルだから私の心が乱されることなどない。
これが当たり前といえばそれまでだが、あのA先生のすったもんだの葛藤があったから、今の満足度が極上に感じられるような気もする。
こうして振り返ると、「転院の決意を固めさせてくれてありがとう」という感謝の気持ちがわずかながらも芽生えてきそうにもなる。A先生がいなければ、いまもほどほどの満足度でK医大付属病院に通っていたかもしれないのだから。
とはいえ医師ならば、患者との情報の非対称性に配慮した言動をとるべきだというまっとうな観点からすると、どう考えてもA先生の態度は褒められたものではないと、腹立たしく思う気持ちが蒸し返されてもくる。
発見いっぱい原田病日記|その9|悩んだすえに転院して半年。なぜ、あれほど悩んだのかを振り返る
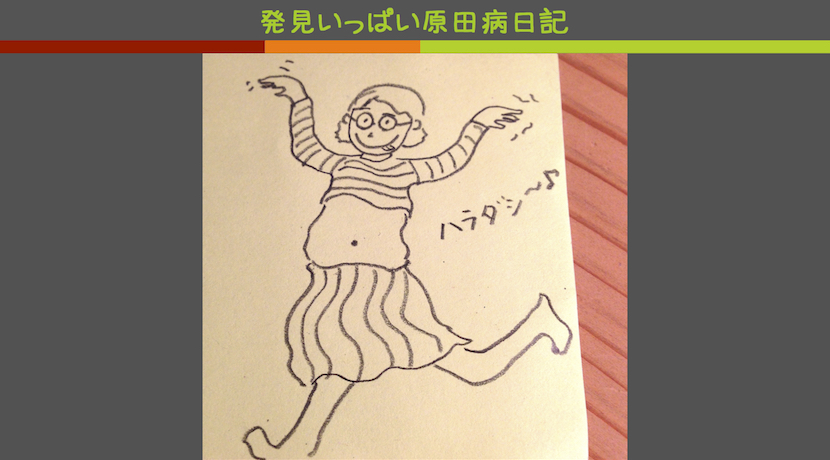 原田病日記
原田病日記
